「回線トラブルもなく、オンライン研修も無事に終わってよかった」
「でも、、、なんだか手応えがないな…」
コストも抑えられ、場所を選ばないオンライン研修は、今や当たり前の選択肢になりました。しかし、その一方で、「本当にこれで効果が出ているんだろうか?」という漠然とした不安を感じてはいませんか?

- 参加者の反応が薄く、ちゃんと聞いているのか分からない
- 「カメラをオフにさせてください」という人が多く、一体感が生まれない
- グループワークをしても、対面の時のように盛り上がらない
- 研修後のアンケートには「分かりやすかった」と書いてあるけど、本音はどうなの…?
対面研修のような「熱量」が感じられず、ただ講師が一方的に情報を配信しているだけに感じる。そのお気持ち、よく分かります。もし「オンライン研修は対面より効果が劣る」と感じているなら、それは非常にもったいないことかもしれません。
オンラインには、オンラインならではの「壁」が存在します。そして、その壁を乗り越えるための「秘訣」も、ちゃんと存在するのです。
この記事では、なぜオンライン研修が「効果なし」と感じやすいのか、その原因を解き明かし、参加者の集中力を切らさず、学びを最大化するための具体的な5つの秘訣を、詳しくご紹介します。
なぜ? オンライン研修で「効果が出ない」と感じる3つの壁
まず、敵を知ることから始めましょう。オンライン研修には、対面研修にはない、特有の「壁」が3つ立ちはだかっています。これを知るだけで、対策の立て方が明確になります。
第1の壁:抗えない『集中力の壁』
最大の敵は、参加者の「集中力」が続かないことです。自宅などのプライベートな空間は、オフィスの会議室とは違い、誘惑で溢れています。スマホの通知、急な来客、未就学のお子さんなど。
また、対面と違って他の参加者の視線がないため、つい他の作業をしてしまう「内職」がしやすい環境でもあります。これでは、研修内容が頭に入っていくはずもありません。
第2の壁:見えない『コミュニケーションの壁』
私たちは普段、言葉そのものだけでなく、相手の表情や声のトーン、場の空気といった「非言語情報」から、多くのことを読み取っています。しかし、オンラインではそのほとんどが失われてしまいます。
参加者の「なるほど!」という納得の表情や、「うーん」と悩む空気感が伝わりにくくなります。「リアクションは大きめにお願いします!」とアナウンスをしても、変わらないことも少なくありません。参加者同士も、休憩中の雑談のような偶発的なコミュニケーションが生まれにくく、心理的な距離が縮まりにくいのです。
第3の壁:孤独に感じさせる『一体感の壁』
研修効果を高めるためには、他の受講者との交流から生まれる気づきが欠かせません。しかし、オンライン研修では、そのための「一体感」が作りづらく、参加者一人ひとりが画面の前の「個」として孤立しがちです。
特にカメラをオフにしていると、自分がその場の一員であるという意識が薄れ、「自分は視聴者でいいや」という受け身の姿勢になりやすくなります。これでは、活発な議論や深い学びは生まれません。
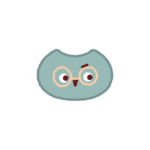 フーム
フームなるほどな。「集中力」「コミュニケーション」「一体感」か…。どれもオンライン研修で「あるある」と感じる課題だ。便利さの裏返し、というわけか。
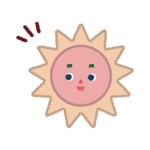
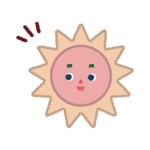
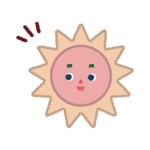
本当だね!ただ配信するだけじゃダメで、これらの「壁」を意識的に壊しにいく工夫が必要ってことか…。なんだか、ただの「配信係」になってたかも、私。
オンライン研修の難しさは、ツールの問題ではなく、参加者が置かれる「集中しにくい環境」と、参加者が陥りやすい「孤独感」にあります。ですが、これらは事前準備とカリキュラム、講師選定で十分クリアできる問題です。
オンラインの壁を壊す!学びを最大化する5つの秘訣
オンライン特有の「壁」が分かれば、あとは対策を打つだけです。これからご紹介する5つの秘訣を実践すれば、あなたの会社のオンライン研修は、参加者が前のめりになる「特別な時間」に変わります。


秘訣1:『対面より、さらに細かく』を意識する
オンラインでは集中力が切れやすい、という前提に立ちましょう。カギは「時間管理」です。90分話し続けるような構成は絶対にNG。対面以上に、こまめな休憩と緩急が重要になります。
- 休憩はこまめに: 「60~80分研修→10分休憩」のように、短めのサイクルを意識する。
- 講義は短く、ワークは長く: 講師が一方的に話す時間は10~15分程度に区切り、チャットへの書き込みやグループワークの時間をこまめに挟みましょう。
秘訣2:『全員参加』の仕掛けをデザインする
「聞いているだけ」の時間を作らないことが鉄則です。オンラインツールに搭載されている機能をフル活用し、参加者を巻き込み続けましょう。
- チャット機能: 「今の説明で分かったことを、一言でチャットに書いてください!」と投げかける。
- 投票・アンケート機能: 匿名で回答できるため、本音を引き出しやすい。
- ブレイクアウトルーム: 3~4人の少人数グループに分ければ、誰もが発言せざるを得ない状況を作れます。「話すのが苦手な人」も、少人数なら安心して話せます。
秘訣3:『あえて雑談』の時間を設計する
対面なら自然に生まれる雑談も、オンラインでは意識的に作る必要があります。この雑談こそが、心理的安全性を高め、活発な意見交換の土台になります。
- 研修冒頭の自己紹介タイムをしっかりと: オンライン上での自己紹介が苦手な方のために、自己紹介のテーマは指定しましょう。
- 自己紹介のテーマ: 「名前・仕事内容」「業務の課題」などの仕事だけのテーマにせず、「最近ハマっていること」「楽しかったこと」など、仕事以外のテーマで自己紹介をさせると、意外な共通点が見つかり盛り上がります。
- 交流することを推進する:研修内容だけにとどまらず、グループワークの隙間時間にお互いの仕事のことを共有して、交流することも促すといいでしょう。普段話せない方との交流は、参加者の視点視座を広げることにつながります。
秘訣4:『視覚』に徹底的にこだわる
参加者の情報は、ほぼ100%「画面」から入ってきます。だからこそ、画面に映るものすべてに気を配る必要があります。
- スライド資料: 1スライド1メッセージを基本とし、文字を大きく、少なく。図やイラストを多用して、直感的に理解できるように工夫する。
- カメラの映り方: 講師だけてなく、参加者こそカメラにどう映るかは重要です。口元から下が見えない、逆光で表情が見えない、角度がキツすぎると、話がしにくい映り方になります。(冒頭のアナウンスの段階で「カメラの画角調整」を促すといいでしょう)
秘訣5:一番影響が大きいのは『講師ファシリテーション』
登壇する講師のファシリテーション力は無視できません。受講者の意見を引き出す力、魅力的に伝えるスピーカーとしての話力、対面研修以上に求められます。外部講師に依頼する場合は、必ず事前にオンラインでの顔合わせを実施し、その雰囲気を体感されるといいでしょう。
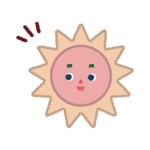
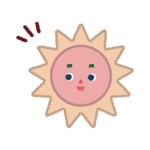
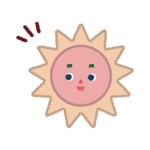
なるほどー!ただツールを使うだけじゃなくて、休憩のタイミングや資料の見せ方まで、全部が「設計」なんだね!



その通りだね。オンラインの『制約』は、工夫次第で乗り越えられる。むしろブレイクアウトルームのように、オンラインだからこそ『全員が均等に話せる』という強みに変えることもできるんだな。
効果的なオンライン研修、自社だけでできますか?
「オンラインは効果がない」のではなく、「効果を出すためのやり方」が存在します。
しかし、同時にこうも感じませんでしたか? 「こんなに緻密な設計とファシリテーション、うちの社員だけではとても無理だ…」その通りです。効果的なオンライン研修の運営には、対面研修とは全く異なる専門的なスキルと、入念な準備が必要になります。
もし、あなたが「名前だけのオンライン研修」を卒業し、本当に価値のある学びの場を創りたいと本気で考えているなら、ぜひ一度、マナビポップ株式会社にご相談ください。
対面研修で培った「参加者を主役にする」ノウハウを、オンライン研修にも応用しています。オンラインの「壁」を知り尽くしているからこそ、それを乗り越え、むしろ強みに変える研修設計が可能です。

